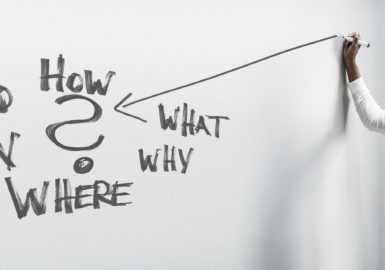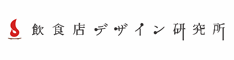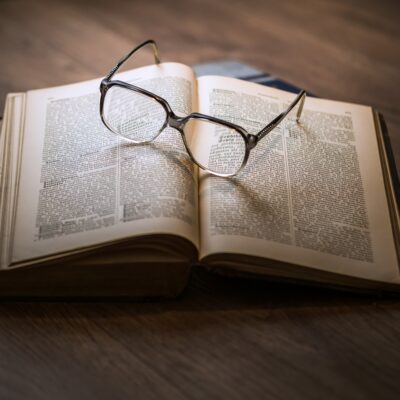飲食店へ行く人のニーズが変化してきていると実感

「コロナによって変わったわけではない!」
コロナがおきてから、飲食店がテイクアウトしたり、デリバリーしたり、クラウドキッチンを作ってみたりしていますよね。でも、これってコロナによって、色々と変化したようにみえているだけで、実はもっと前から変わらなくてはいけない状況だったんです。
俯瞰で日本だけではなく、世界の外食をみよう!
ただ、時代の変化のスピードが上がっただけなんです。そして、これから先、日本だけをみている経営者は知らないうちに取り残されるでしょう。要するに外食産業のビジネスモデルが変わっていくということです。
コロナで迷走?!これからどんなお店を出したらいいんだろ?という疑問

私たちがずっとデザインし研究してきた小さな個店の飲食店は、このコロナでどういった舵取りをしたのだろうか?
人の習慣は、なかなか戻らない!?
営業を停止し、顧客を失った店舗。だって、飲食店っていつもいくリピーター命なはずなのに、店がお休みなら習慣化がなくなってしまいます。自粛があけたからって、人々の習慣が元に戻るとは限りません。
慌ててテイクアウトをしたけど、利益が薄く結局やめた店舗
テイクアウトって言ったって、いきなり商品開発もせずに、今まで通りのメニューを弁当に詰めたからって、売れるわけではありません。だって、競合にコンビニや弁当屋さんというめっちゃ強い強豪がいるんですもん!そこは、ずぅ~と、考えに考え抜いた美味しいテイクアウトをしてますから。
実際、私もコロナ初期にテイクアウトやデリバリー頼みましたけど、冷めてるし、硬いし、正直美味しいと言えるものではなりませんでした。最近、だんだんと美味しいお店が増えてきましたけど。要するに、今までの飲食店は出来立てが美味しい状態で、メニューを作っていたのに対して、テイクアウトやデリバリーは、購入してから家に持って帰るまでや運ばれるまでに時間がかかります。ここの時間を考慮されたメニュー開発をしなければならないのです。
場当たり的なテイクアウトやデリバリーでは意味ない!
しかも、デリバリー手数料はそれなりに支払わないといけないし、テイクアウトで支払う客単価は、お客様の感覚的なコスト(コンビニやスーパーや弁当屋が出している金額)は、少し安めに設定されています。要するに、慌てて場当たり的に考えたビジネスモデルでは、この危機に対応できなかったわけです。
みんなが求めている店舗ってなんだろ?
「では、どういった店舗を出店すればいいんだろうか?」
それを考えるヒントは、
①食に対する価値って、今現在どう変わったのか?
②今一番発展しているITツールで、役に立つものはないのか?
③どうやって飲食店を選んでいるんだろうか?
この3つのポイントを考えることで、見えてくるんです。そこで「フードテック革命」という本に出会いました。まさに今必要な考え方と情報なのでは!?と思い、その中で私の実体験と重なり合うところだけをピックアップしてお話しします。(実感ないと具体的に書けないので、、、)
食に対する価値観が、世界的に変わってきた!

飢餓って最近あまり聞かないなぁ〜と思ったら、、、
私の感覚(ちょっと古い考え)では、「ご飯も食べれない貧しい子供がいるから、食べ物は粗末にしちゃダメ!」と言われて育ってきました。(アフリカとかのガリガリの子供の映像みながら)
でも、ちょっと調べてみると、飢餓に苦しんでいる人が、かなり減ってきています。これって、日本で言うと「安く、早く、美味しいものを!」といって飲食店がしのぎを削って、発展してきたことが世界でも起きていて、ご飯がない地域にも食が渡り始めた結果が出たんだと思います。これは素晴らしいことですよね~。
今の食の問題は肥満って知ってました!?
でも、アメリカでは肥満の人口がどんどん増えて、食の問題がかなり前から課題になっていたそうです。そう思えば、私の母も「もっともっとたくさん食べてなさい!」とお腹いっぱいなのに、食べていた記憶もあります。結果、父も母も肥満気味、そして私も、、、
お腹を満たすより健康を考えた食事に
なので、私の息子には「お菓子やファーストフードはほどほどにして、野菜やお肉食べなさい」と言っています。さらには「無理して食べなくていいよ」とも言います。これって、お腹を満たすための食事というより、健康のための食事になったということです。これって食糧が簡単に安く手に入るようになったからです。
「もっと美味しいもの、もっと早く効率的に、便利な場所に!」を求められた時代
そう思えば、私の両親は戦後昭和の時代を生きてきました。物が少なく、より良いものを作り続けて、発展してきました。もちろん食事だって、「もっと美味しいもの、もっと早く効率的に、便利な場所に!」と駅前中心に発展してきました。
ものが溢れたのは、努力の賜物。。でも「おいしさ」「効率化」「利便性」に価値がない?!
それが、今やモノが溢れた時代。どのお店に行っても美味しいわけです。そもそも不味い店は、とうの昔に潰れています。競合店が値段を落とせば、こっちも!と価格競争が生まれます。新しい専門料理店ができれば、こっちも!と新たな業態を作ります。さらに、コスト競争が進み、働きたい人も減り続け、人件費削減するために効率的なオペレーションを生み出してきました。こうやって、出来上がったのが、今の日本の外食産業なんです。
なので「おいしさ」「効率化」「利便性」には、競合店との差別化するための価値としては、もうほとんど残っていないです。でも、「おいしさ」は最低ラインになっちゃてるんです。日本では。
個々に合わせた商品提供が可能に?!
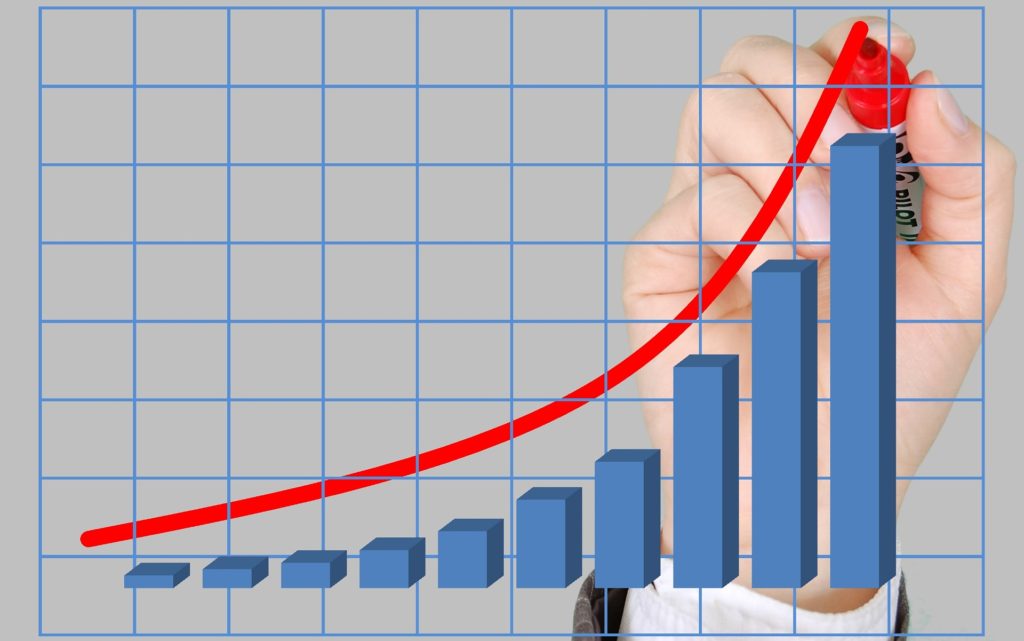
コロナで発見した、家での食事の価値がヒントに!
では、どういう価値が、これからの時代求められてくるんでしょうか?
コロナ中に自宅で食事を食べるシーンが増えました。みなさんもそうじゃないですか?私は「面倒だなぁ~」「外食のほうが楽だなぁ~」と思いましたが、今では「家での食事も悪くないなぁ~」と思い始めています。私の場合は、家族とのコミュニケーションが増えたことが、とてもメリットと感じています。みなさんはどうでしょうか?実は他にも色々ありそうですよね~。これこそが、外食する新たな価値と関係してくるわけです。
友人や取引先と「最近どうですか?」とたわいもない話をした時に、必ずコロナでの生活の変化がメインのお話になります。そこで、私は食について必ず聞くようにしました。どういう食生活に変化が生まれてきているのかは、とても興味がありましたので。
すると、いろんな意見が聞けたので、ここではその中でも多かった意見をご紹介します。
「料理を楽しみたい!」という意見。それは料理を作るようになった人もいれば、焼肉とかバーベキュー、たこ焼きとか、しゃぶしゃぶとか、作りながら食べるスタイルが楽しいという人もいます。
「家族とのコミュニケーションを楽しみたい!」という意見。これは私と一緒ですね。
「くつろぎながら食事ができる」という意見。これは外食では、ジャージですっぴんで食事はできないですもんね。あと、子供が騒ぐと気を使うので、家だと落ち着いて食べれるという意見もあります。
そうなると、「家の食事では体験できない価値を!」となりそうですが、そうでもないんです。外食はやはり家族以外でも食べに行きやすいですし、プロに作ってもらえますし、片付けもないです。メリットは十分あります。ここでは新たな価値を創出を考えていきます。
「飲食店へ行くことで孤独を解決したい!」という意見。これは一人暮らしの人は、家で食べてもコミュニケーションが取れません。
「フードロスを無くしたい!」という意見。これは社会的な貢献です。実は10代20代の若い世代には、こういう意識が増えているようです。日本ではまだあまり聞きませんが、、、
その他にも「ヴィーガン」「ベジタリアン」「フレキシタリアン」「ペスカトリアン」などなど
多種多様な価値観へと拡がっています。
12つの新たな価値観
12つの新たな価値観があります。(フードテック革命参照)
発見する喜び、快適性、コミュニティー、親しみ、実験、協力、信頼、安心、新しさ、参加、個性の表現、気使う
でも、こんなにたくさんの価値を拾い上げていくのは、無理ですよね~。なので、一つに絞って考えてみたり、共通項を探してみたり、ITツールで解決案を探してみたりするんです。
IT化によって、できることがとても増えたと思うんです。その一つがロングテールという考えのビジネスモデルです。ロングテールって、ほとんど売れないニッチ商品の販売額の合計が、ベストセラー商品の販売額合計を上回るようになることなんです。Amazonがすぐ思いつきますね。
食のロングテールビジネスとは?
「では、食のロングテールビジネスは?」
そう考えるとワクワクしませんか?
例えば、
- あなたの健康状態を把握し、最適なメニュー提案ができる店舗?
- その立地に合わせたメニュー構成?
- 売上に応じて自動的に変化するメニュー?
などなど
要するに、いちいち人がパソコンに入力したり、紙にメモしたりしなくても、自動でデータを拾い上げ、情報整理し、アウトプットさせる仕組みを作るということです。IT化させることで、膨大な情報量を扱えるようになります。今、世界では食ビジネスとして、新たな模索が始まっているのです。
何を買うか?から、誰から買うか?への変化

とはいえ、ちょっと先の未来へいくために、その手前でやらなければ生き残れないのも事実。
では、近々の現状を突破するには、どうしたらいいのでしょうか?
日本ではどこで食べてもそこそこ美味しい。そもそも不味い店は、とうの昔に潰れています。今は、みんな美味しくて、いろんな種類の専門料理があり、コストが安く、さらには家でも美味しいものが食べれるようになってきました。要するに食の美味しさには、日本では、昔のように「美味しい」という価値がなくなってきています。だとしても、不味くては選ばれないのは当然です。
では、どうしたら良いのか?
属人的なお店にすることだと、今の私は思っています。属人的というのは「あの人が紹介するお店だから行ってみよう!」「あのお店が好きだから」「店主が面白いか」「あのお店が私の心地よい場所」などなど、誰だからもしくは、あの店舗だからといったように、モノから人や店(ブランド)で選ぶような価値観に変わってきたのです。「何を食べようか?」より「あの店で食べようよ!」といわれるお店が、人気店へと変わっていくのです。
まとめ
①「効率性」「おいしさ」「利便性」の時代から「発見する喜び」「快適性」「コミュニティー」「親しみ」「実験」「協力」「信頼」「安心」「新しさ」「参加」「個性の表現」「気使う」の12種類の価値観へ変わっていく
②IT化によって、飲食店もロングテールを使った店舗が作れるようになった
③「何を食べようか?」より「あの店で食べようよ!」といわれる属人的な店舗が勝てる時代になる
美味しくって、便利な場所で、早く、安く食べれるという争いはやめよう!世界で起きている外食産業を参考に、12種類の価値観から新しい飲食店を作ってみましょう!